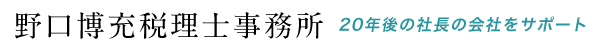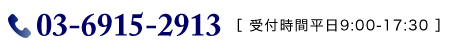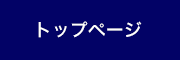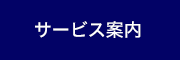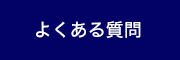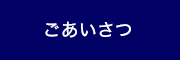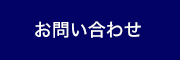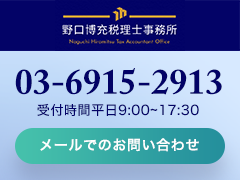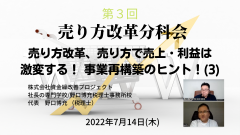【社長の専門学校】第3回 売り方改革分科会その1
目次
- Z世代の特徴とビジネスへの影響
- 進化するECサイト
- OMO活用と顧客との関係構築
Z世代の特徴とビジネスへの影響
現代の経営では「最も変化に敏感なものが生き残る」という進化論が語られるように、小さな変化を見逃さないことが重要です。
最近注目される「Z世代」(10代前半から25歳程度の若者)は、今後の消費主役として大きな経済影響力を持つ世代です。
しかし、日本国内では少子化や賃金抑制、消費意欲の低下から「車は買わない」「お酒は飲まない」といった傾向が見られます。
一方で、Z世代は「シェアとミー」という過剰な自意識や審美眼の高さを特徴とし、広告や商品が少しでも共感を欠くと興味を失うと言われています。
企業がZ世代をターゲットにするには、彼らに「権威を委譲し、協働する」という視点が必要です。
例えば、若者に発信の場を提供し、一緒に商品やサービスを作り上げることで、彼らの心をつかみ消費行動につなげることが求められます。
最近注目される「Z世代」(10代前半から25歳程度の若者)は、今後の消費主役として大きな経済影響力を持つ世代です。
しかし、日本国内では少子化や賃金抑制、消費意欲の低下から「車は買わない」「お酒は飲まない」といった傾向が見られます。
一方で、Z世代は「シェアとミー」という過剰な自意識や審美眼の高さを特徴とし、広告や商品が少しでも共感を欠くと興味を失うと言われています。
企業がZ世代をターゲットにするには、彼らに「権威を委譲し、協働する」という視点が必要です。
例えば、若者に発信の場を提供し、一緒に商品やサービスを作り上げることで、彼らの心をつかみ消費行動につなげることが求められます。
進化するECサイト
ECサイトの活用方法は急速に進化しており、企業の事例から学ぶべきポイントが多くあります。
個人事業主の事例:初期投資を抑えるため、まずはAmazonや楽天市場などの大手プラットフォームを活用し、軌道に乗った段階で自社ECサイトを立ち上げる戦略が紹介されました。
アシックスの取り組み:自社ECサイトで顧客データを収集し、9万人の部活動データを基に成長予測を行い、最適な靴を提案。購入履歴から新たなデータを蓄積し、精度を高めています。
日本ハムの工夫:直営ECサイトを複数運営し、食物アレルギー情報を一元化したサイト「Table for All」を展開。幕開け(クラウドファンディング)を活用し、在庫リスクを抑えつつ顧客を獲得する手法も取り入れています。
個人事業主の事例:初期投資を抑えるため、まずはAmazonや楽天市場などの大手プラットフォームを活用し、軌道に乗った段階で自社ECサイトを立ち上げる戦略が紹介されました。
アシックスの取り組み:自社ECサイトで顧客データを収集し、9万人の部活動データを基に成長予測を行い、最適な靴を提案。購入履歴から新たなデータを蓄積し、精度を高めています。
日本ハムの工夫:直営ECサイトを複数運営し、食物アレルギー情報を一元化したサイト「Table for All」を展開。幕開け(クラウドファンディング)を活用し、在庫リスクを抑えつつ顧客を獲得する手法も取り入れています。
OMO活用と顧客との関係構築
OMO(Online Merges with Offline)の発想を取り入れた事例も増えています。
広島のファッション店舗「ヒール&トゥー」:ネット通販とリアル店舗を組み合わせ、メールで雑談を交えたコミュニケーションを行うことで、顧客との距離を縮めています。メールのやり取りで信頼関係を築いた後、実店舗で顔を合わせると自然な接客が実現し、セール値引きせずに販売が成立しています。
また、メーカーの主導権争いが新たな動きを見せており、IoT技術を活用して製品の使用状況データを直接メーカーが収集することが可能に。これにより、メーカーが顧客行動の把握を主導し、販売促進の主導権を握る可能性が高まっています。
自社の取り組みを見直すきっかけとして活用し、既存の戦略にどう取り入れるかを考えるヒントにしていただければ幸いです。
広島のファッション店舗「ヒール&トゥー」:ネット通販とリアル店舗を組み合わせ、メールで雑談を交えたコミュニケーションを行うことで、顧客との距離を縮めています。メールのやり取りで信頼関係を築いた後、実店舗で顔を合わせると自然な接客が実現し、セール値引きせずに販売が成立しています。
また、メーカーの主導権争いが新たな動きを見せており、IoT技術を活用して製品の使用状況データを直接メーカーが収集することが可能に。これにより、メーカーが顧客行動の把握を主導し、販売促進の主導権を握る可能性が高まっています。
自社の取り組みを見直すきっかけとして活用し、既存の戦略にどう取り入れるかを考えるヒントにしていただければ幸いです。